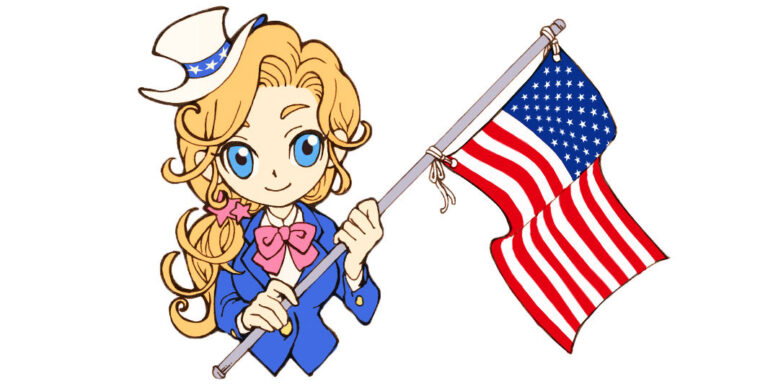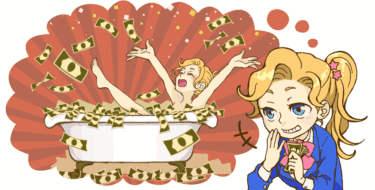よく耳にするシャープレシオですが、あまり意味が分かっていなかったのでChatGPTに整理してもらいました。間違っているかもしれないので参考程度にどうぞ。
目次
Ⅰ. シャープレシオ入門(やさしく・要点だけ)
1) これは何の数字?
「リスク1単位あたり、無リスクよりどれだけ稼げたか」を表す効率スコア。計算式は以下のとおり。
Sharpe=Rp−Rf/σp
- Rp:ポートフォリオの平均リターン
- Rf:無リスク金利(短期国債など)
- σp:ポートフォリオのリターンの標準偏差(ボラティリティ)
数値が大きいほど「効率よく儲けた」と評価されます。
無リスク金利は短期国債(金利)を使うのが定番です。日本円なら日本のT-Bill、米ドルなら米国T-Bill。日本の3カ月物は直近約0.45%、米国の3カ月物は**約3.7~3.8%**です。
2) 数字の読み方(だいたいの目安)
- 0.5前後:まあ良い
- 1.0:良い
- 2.0:とても良い
- 3.0:例外的に優秀
(期間・戦略で解釈は変わります)
3) 年率化のコツ
日次データなら平均×252、標準偏差×√252で年率化(同様に月次は×12と×√12)。結果のシャープも**√(期間数)**に比例して伸縮します。
4) よくある落とし穴
- 金利・通貨の合わせ方:評価通貨(円 or ドル)と無リスク金利の通貨・頻度を揃える。
- 分布の歪み:オプション売りや暗号資産のようにテールが重い戦略は、シャープが実態より良く見えることがある。
- 期間比較の一貫性:同一の期間・頻度で比較。
- 為替ヘッジ:ヘッジは概ね“金利差”がコストに反映される(カバードIRP)。米ドル⇄円では金利差が縮むとヘッジコストも下がる傾向。
Ⅱ. いまの市場前提(ざっくりファクト)
- 無リスク金利:日本3M T-Bill ≈ 0.45%、米国3M T-Bill ≈ 3.7–3.8%(2025/10末)。
- ボラティリティの目安:直近データでは、ビットコインの年率ボラ ≈ 50–60%、ゴールド ≈ 15%、**世界株 ≈ 10%**周辺。
- 相関の直感:
- ゴールドは株の下落期に**相関低下(避難先の性質)**が出やすい。
- ビットコインは近年、株との短期相関が0.4–0.6程度に上がる局面があった(完全な分散にはならないが、長期では独自要因も)。
目的は「期待超過リターン ÷ リスク」を最大化すること。相関の低い資産を混ぜて分母(ボラ)を押し下げ、期待超過が見込める資産をほどよく配合します。
Ⅲ. 「日本株+米国株+ゴールド+BTC」でシャープ最適化プラン
評価通貨は円想定。為替は“半分だけヘッジ”を基本にし、ヘッジ比率はコストと相場環境で見直す(米金利低下でUSDヘッジコストは低下方向)。
A) ベースライン(“Sharpe第一”の汎用解)
- 日本株(円):20%
- 米国株(USD・50%ヘッジ):45%
- ゴールド(円建て or USDヘッジ型):25%
- ビットコイン:5%
- T-Bills/短期MMF(円 or USD):5%
狙い
- コアは株だが、25%の金でボラを抑え下落緩衝。
- BTCは5%上限で“右側リターン”を取りつつ、過度なボラを抑制(BTCの高ボラを踏まえた“スパイス”程度)。
- 50%為替ヘッジで「リスク低下」と「 carry コスト」の中間を取る。ヘッジ費用感は金利差に連動。
B) ディフェンシブ(下振れ耐性最優先)
- 日本株15% / 米国株40%(50–70%ヘッジ) / ゴールド35% / BTC2% / T-Bills8%
→ 株のウェイトを落とし、金と短期金利で**分母(σ)**を縮小。相場急落期の相関低下(ゴールドの“逃避”性)も期待。
C) アグレッシブ(超過リターン重視)
- 日本株20% / 米国株55%(ヘッジ30%) / ゴールド15% / BTC10% / T-Bills0%
→ 期待超過リターンは伸びやすいが、ボラ拡大でシャープはベースラインと拮抗 or 低下も。BTCの高ボラに注意。
実務オプション
- 金の持ち方:現物連動ETF(例示:GLD/IAU/SGOL/BAR等の仕組みは同様)や金先物ETF。コストと流動性で選択。
- BTCの持ち方:スポット型ETFや現物。ポートの**2–5%**を基本レンジに(再上限10%)。
- 米株の為替:ヘッジ比率を可変(例:ヘッジコストが高ければ30%へ、低下すれば70%へ)。ヘッジコストは概ね日米金利差に依存。
Ⅳ. ルール設計(シャープを“維持”する運用術)
- バンド・リバランス:各資産の±20%相対乖離(例:25%目標の金が30%超)でトリム/買い増し。
- 四半期チェック:
- 無リスク金利(日本・米国)、ヘッジコスト、相関の変化を確認。
- Fed/日銀の金利動向でヘッジ比率を見直す(ヘッジコスト低下ならヘッジ厚めがシャープ有利)。
- ドローダウン・ガード:
- 株式が目標から**+5pt**以上に膨らんだら一部を金/T-Billsへ。
- BTCは目標比+50%超で必ず一部利確(ボラ管理)。
- 評価通貨を固定:円ベースで年率シャープを継続計測(同一通貨・同一頻度・同一金利で)。
Ⅴ.まとめ
- 金は“シャープを底上げする緩衝材”、BTCは“少量のブースター”。
- 米株は半ヘッジから入り、金利差が縮むほどヘッジ厚めが有利になりやすい。
- 四半期ごとに再点検し、±20%相対乖離で機械的にリバランス。