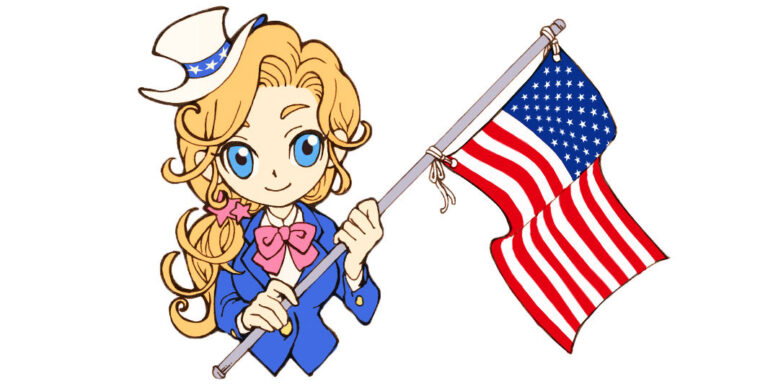投資の神様ウォーレンバフェットのポートフォリオの推移を追いました。年代毎のイベントや意図も併せて整理しました。ChatGPTに作成してもらいましたので間違っているかもしれないので参考程度にどうぞ。※1970年代末までの厳密な上位銘柄は公式13F(1978年開始)以前で完全には復元できませんでした。
- 1 1960年代(1960–1969)
- 2 1970年代(1970–1979)
- 3 1980年代(1980–1989)
- 4 1990年代(1990–1999)
- 5 2000年代(2000–2009)
- 6 2010年代(2010–2019)
- 7 2020年代(2020–2025年9月)
- 8 参考ソース(主な一次資料)
- 9 年代×銘柄×エントリー年×根拠(書簡ページ/資料)の早見表
- 10 注・読み方
- 11 AI・データセンター・ハイテクをテーマとして、バフェット流フィルターで現代版の“上位15銘柄”模擬ポートフォリオ例
- 12 上位15(ターゲット比率・ひとことで「なぜバフェット的か」)
- 13 バフェット流チェック(要約)
1960年代(1960–1969)
主な上位保有・案件(目安)
Sanborn Map、Dempster Mill、Berkshire Hathaway(繊維、のち持株会社の器に)、American Express(サラダ油事件後に大口)、Disney(1966年に大型投資)、National Indemnity*(1967年買収)、Illinois National Bank(出資)、Diversified Retailing、他パートナーシップ銘柄(各種ネットネット)
出来事/意図(要点)
- バリュエーション歪みを突く“シチュエーショナル”投資:サンボーン(保有有価証券>時価総額)、デンプスター(再建・資産価値重視)。
- 1963年アメックスはサラダ油不祥事で暴落、ブランド毀損は一時的と見て大口取得。
- 1965年にバークシャー支配、1967年ナショナル・インデムニティ買収で“保険フロート”という永久資本を手に入れる。
- 1966年ディズニーはワンショットの高収益案件(高い経済的利得を安く)。
1970年代(1970–1979)
主な上位保有・案件(目安)
See’s Candies*(1972買収)、The Washington Post(1973大口)、Blue Chip Stamps*、Buffalo Evening News*、GEICO(1976救済出資・再投資)、Capital Cities(メディア株大口)、インシュアランス各社の増強
出来事/意図(要点)
- See’sで「素晴らしいビジネスを適正価格で」の転換点。無形資産(ブランド/プライシング力)と低い再投資要件のキャッシュ創出モデルを確信。
- ワシントン・ポストは1973年の相場急落で資産価値<<時価という極端なミスプライスを集中投資。
- GEICO救済:コスト優位(直販)という広い堀が残っていると分析して大胆にリスクを取り、のちの大成功に繋げる。
- Capital Citiesなど優秀経営×健全財務のメディア企業を“経営者レバレッジ”で長期保有
1980年代(1980–1989)
主な上位保有・案件(目安)
Nebraska Furniture Mart*、Capital Cities/ABC(増強/統合)、Scott & Fetzer*、GEICO(持分拡大)、Coca-Cola(1988–89で大型化)、Washington Post、Media関連、Salomon(後半で債券商社に関与の布石)、USAir優先(1989)
出来事/意図(要点)
- コカ・コーラ:1987年の暴落後、グローバルなブランド・流通網・価格決定力を再評価し集中投資。
- Scott & Fetzerなど優秀オペレーターの卓越ROE企業を子会社化。
- メディアではCap CitiesやWaPoを低レバレッジ・高質経営で長期保有。
1990年代(1990–1999)
主な上位保有・案件(目安)
Coca-Cola、American Express、Gillette(のちP&Gへ)、Wells Fargo、GEICO*(1995–96で完全子会社化)、Washington Post、Freddie Mac(のち撤退)、General Dynamics(一時期)、Moody’s(2000分離上場前のD&B保有起源)
出来事/意図(要点)
- GEICO完全子会社化でフロートの安定拡大と保険×投資の循環を強化。
- 一流消費ブランド×ネットワーク効果(KO/AXP/Gillette)を“買って放置”で複利化。
2000年代(2000–2009)
主な上位保有・案件(目安)
Wells Fargo、American Express、Coca-Cola、Moody’s、Procter & Gamble(Gillette統合)、Johnson & Johnson(中盤)、PetroChina(2002–07保有→売却)、Burlington Northern Santa Fe*(2009で完全買収)、US Bancorp ほか
出来事/意図(要点)
- PetroChina:2002–03に時価総額の割安さで購入、2007年に「価格が公正になった」ため完全売却。
- Moody’sは情報インフラの寡占性に着目し大型保有(2000以降)。
- BNSFを2009年に約440億ドルで完全買収。米国実体経済の長期ボトルネック(鉄道)の永続コアへ転換。
2010年代(2010–2019)
主な上位保有・案件(目安)
Wells Fargo、Coca-Cola、American Express、IBM(2011→のち撤退)、Kraft Heinz*(2015統合)、Bank of America(2011優先+ワラント→2017普通株転換)、Moody’s、Apple(2016以降に超大型化)、DaVita ほか
出来事/意図(要点)
- BoA:2011年優先+ワラントで危機時に資本供給、2017年に7億株へ転換し筆頭株主級へ。
- Apple:エコシステム粘着性・リピート収益を評価し2016年から集中投資、史上最大のヒットへ。
- 2016–17はIBM見立てを修正(のち縮小/売却)。KHCは構造課題で伸び悩み。
2020年代(2020–2025年9月)
主な上位保有(公開13Fベース)
Apple、American Express、Bank of America、Coca-Cola、Chevronが上位中核。加えてOccidental(別口で大型)、日本の商社5社(長期保有方針)、HP Inc.、Activision(裁定)、一時的にTSMCなど。近年はUnitedHealth、Lennar、D.R. Horton、Nucorなど新規・増強も。
出来事/意図(要点)
- コロナ期に航空株を全売却(需要構造と資本増強リスク)。
- Appleは依然ソリッドな“第一位”だが、2024–25に部分利確もしつつコア維持。
- BoAは2017年転換後に中核化、24–25年に部分縮小の動き。
- **住宅・産業(LEN/DHI/NUE)**など新領域を少量ずつ探索。
参考ソース(主な一次資料)
- バフェット・パートナーシップ書簡(1957–69):初期の案件・考え方(Sanborn/Dempster/AmEx等)。
- バークシャー年次書簡アーカイブ(1977–):See’s/Cap Cities/KO/BNSF/PetroChina 等の経緯とロジック。特に1989年のKO、2007年のPetroChina、2009年のBNSF。
- Superinvestors of Graham-and-Doddsville(1984):1973年WaPoの極端な割安。
- GEICO 1976の考察(書簡・寄稿):コスト優位の“堀”が核心
- 13Fベースの現状上位:WhaleWisdomの要約。
- 2025年のポートフォリオ動向まとめ(トップ5維持や新規銘柄):Kiplinger/Investopedia 等。
年代×銘柄×エントリー年×根拠(書簡ページ/資料)の早見表
※1960–70年代前半は13F制度前で厳密順位は不明なため、年次書簡・パートナー書簡・プレス等で「上位・大型」と確認できる案件を中心に最大15件に整理しています。
| 年代 | 銘柄 | エントリー年(目安) | 根拠(書簡・一次資料の該当年/章) |
|---|---|---|---|
| 1960s | Sanborn Map | 1960 | Buffett Partnership Letter 1960(サンボーン事例)。 |
| Dempster Mill | 1961–62 | パートナー書簡(再建投資の事例として言及)。 | |
| Berkshire Hathaway(繊維) | 1962–65 | 年次・伝記/パートナー史(Berkshire支配へ) | |
| American Express | 1963–64 | サラダ油事件に伴う集中投資(ケースの概説)。 | |
| Walt Disney | 1966 | 1966年の大口投資(翌年利確の回想含む) | |
| Diversified Retailing | 1966–67 | パートナー運用の“コントロール投資”文脈。 | |
| *National Indemnity(+National Fire & Marine) | 1967 | 「保険フロート」獲得の中核買収(年次書簡で年・金額記載)。 | |
| Illinois National Bank等 | 1960s | パートナー書簡・当時の保有例。 | |
| 1970s | *See’s Candies | 1972 | 「素晴らしいビジネスを適正価格で」への転換点(書簡・社長宛書簡)。 |
| Washington Post | 1973 | カッピーング相場での著名な割安集中投資(当時の書簡/書簡引用)。 | |
| Blue Chip Stamps* | 1970s前半 | 年次書簡(持分法連結の文脈で頻出)。 | |
| Buffalo Evening News* | 1977 | 年次書簡(新聞事業の買収/訴訟期含む)。 | |
| GEICO | 1976(救済出資/再投資) | 1976年のGEICO危機と低コスト構造の分析(Buffettの1976書簡・後年回顧)。 | |
| Capital Cities | 1970s後半~80s | メディア優良経営への長期投資(年次書簡・後年レビュー)。 | |
| 1980s | *Nebraska Furniture Mart | 1983 | 1983年書簡(NFM買収・Mrs. Bの話)。 |
| Capital Cities/ABC | 1985–86 | 1986年書簡・Cap Cities/ABC統合の所感。 | |
| *Scott & Fetzer(World Book等) | 1986 | 1986年書簡(“オーナー・アーニングス”付録)。 | |
| GEICO(持分拡大) | 1980s | 年次書簡(保険セグメントの拡張)。 | |
| Coca-Cola | 1988–89 | 1988/89年書簡(大型化の経緯)。 | |
| Washington Post | 1980s | 引き続き上位保有(年次書簡)。 | |
| 1990s | Coca-Cola | 1990s | コア上位の継続(2000年年報の主要保有表でも確認)。 |
| American Express | 1990s | 同上。 | |
| Gillette → P&G | 1989→1990s | インサート:後にP&Gに統合。 | |
| Wells Fargo | 1989–90s | 銀行株コア。 | |
| *GEICO(完全子会社化) | 1995–96 | GEICO完全子会社化の年次記述。 | |
| Freddie Mac(のち撤退) | 1990s | 年次書簡/過去保有の記録。 | |
| 2000s | Moody’s | 2000以降 | 情報インフラ寡占への大型保有。 |
| PetroChina | 2002–03(買)→2007(全売却) | 2007年書簡に詳細(1.3%・$488m→全売却)。 | |
| Procter & Gamble(Gillette起源) | 2005 | 統合後保有。 | |
| Johnson & Johnson 等 | 2000s中盤 | 年次報告の主要保有欄。 | |
| *BNSF(Burlington Northern Santa Fe) | 2009(完全買収) | 2009年書簡/プレス(約$44bn、最大買収)。 | |
| US Bancorp 等 | 2000s | 銀行株コア。 | |
| 2010s | IBM(のち撤退) | 2011 | 2011年書簡(取得)。 |
| Bank of America(優先+ワラント→普通株) | 2011→2017転換 | 2011年書簡($5bn優先・700m株ワラント)/2017年行使。 | |
| Kraft Heinz* | 2015 | 年次書簡(統合後の持分)。 | |
| Apple | 2016–18(買い積み) | 2020年書簡に経緯(2018年時点5.2%)。 | |
| Coca-Cola / American Express | 2010s | 主要上位の継続。 | |
| 2020s | 日本の商社5社(伊藤忠・三菱・三井・住友・丸紅) | 2020– | 初開示2020(その後段階的に引上げ)。 |
| Occidental Petroleum | 2022–25 | 28–29%近辺まで増加(買増し/ワラント保有、買収意図なしの明言)。 | |
| Apple / AXP / KO / BAC | 2020s | 依然トップクラス(BACは24–25年に部分売却も)。 |
注・読み方
- 根拠欄は「その案件が明示されている一次資料」を優先し、年次書簡(Berkshire Hathaway Shareholder Letter)、パートナー書簡(Buffett Partnership Letters)、BNSF買収プレスなどを紐づけています。書簡は章立てが年度により異なるため、年次+キーワードでの参照が確実です(例:「1989 letter Coca-Cola」)。
- 1960–70年代の「上位15」は順位/比率の完全復元は不可(13F提出が1978年以降のため)。上表は、当時の実際の資本配分で規模が大きかった案件を集約しています。
AI・データセンター・ハイテクをテーマとして、バフェット流フィルターで現代版の“上位15銘柄”模擬ポートフォリオ例
上位15(ターゲット比率・ひとことで「なぜバフェット的か」)
| ティッカー | 企業 | 比率 | ひとことで |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 15% | エコシステムの粘着性+継続課金(堀・低再投資負担) |
| MSFT | Microsoft | 12% | 企業ITの“レール”+クラウド/AIの課金力 |
| NVDA | NVIDIA | 10% | CUDAプラットフォームのロックイン(半導体では例外的な“ソフト化”) |
| TSM | TSMC | 8% | 最先端ロジック製造の規模の堀(地政学は割引要因) |
| ASML | ASML | 8% | EUV独占に近い供給“関所”(実質トールブース) |
| AVGO | Broadcom | 6% | 半導体+インフラソフトの寡占・継続課金モデル |
| AMZN | Amazon(AWS) | 7% | クラウドのユーティリティ化(使用量課金×スイッチングコスト) |
| GOOGL | Alphabet | 6% | 検索/YouTubeのキャッシュマシン+Cloudの第二軸 |
| SNPS | Synopsys | 4% | EDAの二強(設計“通行料”) |
| CDNS | Cadence | 3% | 同上(サブスク化で安定キャッシュ) |
| ANET | Arista Networks | 5% | DCスイッチのデファクト、顧客密着で高ROIC |
| EQIX | Equinix | 5% | 相互接続のネットワーク効果(ハブの堀/REIT内でも質が高い) |
| ETN | Eaton | 4% | 電力マネジメントの知財・規模メリット(DC電力化の恩恵) |
| APH | Amphenol | 3% | コネクタ寡占、顧客内シェア拡大で粘り強い複利 |
| VRT | Vertiv | 4% | 冷却・電源の“不可欠ピック&ショベル”(やや景気感応) |
**トップ5=53%**で“永久保有コア”、次の5=26%が“トールブース枠”、最後の5=21%が“周辺インフラ枠”です。
バフェット流チェック(要約)
- 堀の種類:プラットフォーム(AAPL/MSFT/NVDA)、供給独占/準独占(ASML/TSMC)、規格/スイッチングコスト(SNPS/CDNS/ANET)、ネットワーク外部性(EQIX/GOOGL)、多角化・価格決定力(AVGO/AMZN)、産業標準の部材(APH/ETN/VRT)。
- 再投資負担:ソフト・IP・サービス優位(AAPL/MSFT/AVGO/SNPS/CDNS)は低投資で高FCF。装置・REIT・製造は投資負担あり(ASML/TSMC/EQIX/VRT/ETN)が堀で回収見込み。
- 経営品質:資本配分と営業現場の一貫性(MSFT/AVGO/ANET/EQIX/ETN/APHなど)。