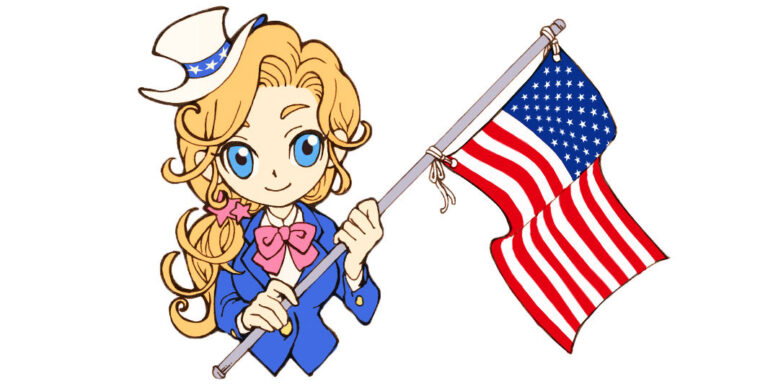株式市場が成長を続ける理由をChatGPTに整理してもらいました。間違っているかもしれないので参考程度にどうぞ。
概要
株式市場が長期で伸びてきたのは「企業の稼ぐ力が(名目で)増え続ける仕組み」だからです。株は“経済の成長+インフレ+企業の再投資”にレバレッジをかけた資産。とはいえ、伸びが何十年も止まった(ように見える)国や時期も実在します。
ぜ伸び続けるのか(メカニズム)
- 実体経済の成長
人口×生産性の伸び=売上・利益の土台。世界の長期データでは、株式は債券・短期金利・インフレを上回ってきました。 - インフレという“名目ブースト”
名目売上・利益が押し上がるぶん、長期の名目収益率は実質より高くなります(米国株は1928年〜の長期平均で名目約10%・実質6〜7%程度のレンジが代表値)。 - 1株あたり利益(EPS)の複利
稼いだ利益を設備投資・M&A・研究開発・配当や自社株買いへ再配分→EPSが複利で伸びる。長期リターンは概ね
トータルリターン ≒ 配当利回り + EPS成長率 ± バリュエーション変化
で分解できます(米国の長期実績は上記平均値が目安)。 - クリエイティブ・ディストラクションと指数入替
弱い企業は指数から外れ、強い新興企業が入るため、代表的指数の“質”は時間とともに更新されます(世界指数でも同様の入替で長期超過が確認されます)。 - リスクプレミアム
変動(リスク)を引き受ける見返りとして、株式は歴史的に現金や国債より高い期待リターンを提供してきました。
「成長が止まる」ことはある?
あります。 「長い停滞・低実質リターン」の形で現れやすいです。
- 米国の長期停滞期(実質)
1966〜1982年は高インフレ期で、主要指数は実質ベースでほぼ横ばい〜低迷。ダウは1966年の高値を名目で超えるのに1982年までかかったのが典型例。 - 日本の超長期停滞からの回復
日経平均は1989年のバブル高値を30年を超えてようやく更新。国・タイミング次第で「数十年規模」の停滞は起こり得ます。 - 制度・地政学リスク
革命・戦争・市場閉鎖・資本規制などで、投資家の権利が損なわれると市場自体が途絶することも歴史上はあります(長期国際データでも“株>債>短期金利>インフレ”は多国で成り立つ一方、国別の明暗は大きい)。 - バリュエーション・金利要因
出発点の割高さ(例:高CAPE)や実質金利上昇は、将来の期待リターンを圧縮し、**「増益でも株価が伸びない」**局面を作ります。
投資家としての実務ポイント
- 世界分散を基本に:一国集中は“日本型の数十年停滞”リスクを抱える。MSCI ACWIや先進/新興の組合せで国リスクを平準化。
- 現実的な期待値設定:世界株の長期実質5%前後+インフレを名目期待のたたき台に(米国単独は実質6〜7%を歴史が示唆)。短期は大きくぶれます。
- 停滞に耐える設計:10〜20年の低迷も想定し、現金・短期債(T-Bill/TIPS)・金などで“生活防衛&リバランス弾”を持つ。
- 源泉はEPS:企業・セクターのROIC>WACC維持、自社株買い・配当の持続性、規模の経済・ネットワーク効果など“EPS複利のエンジン”に着目。
- バリュエーションと金利:出発点の割高さと実質金利が将来10年のレンジを左右。割高局面は期待を下げ、リバランスや積立で時間分散。
まとめ
- 歴史的に株が伸びた主因は、実体経済の成長+インフレ+EPS複利+指数の新陳代謝+リスクプレミアム。
- しかし国や期間によっては10〜30年規模の停滞は普通に起こる(米国66–82、日本89–2024など)。
- よって戦略は、世界分散×現実的期待値×停滞に耐える設計が基本。