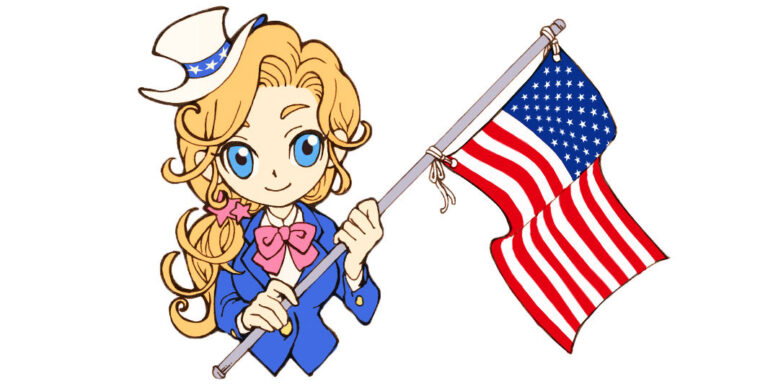「コア銘柄=“長期で持ち続けてよい主力”」をどう選ぶか、その後の投資戦略までを実務フロー+数値基準+運用ルールをChatGPTに整理してもらいました。間違っているかもしれないので参考程度にどうぞ。
目次
- 1 1) コア銘柄の定義(前提)
- 2 2) コア銘柄の選定フロー(7ステップ)
- 3 3) スコアカード(テンプレ)
- 4 4) コアのポートフォリオ設計(構成とサイズ)
- 5 5) 売買・リバランスの運用ルール(実務)
- 6 6) リスク管理の“ガードレール”
- 7 7) 3タイプの「コア構成」ひな形
- 8 8) モニタリング項目(決算で見るべき“定点”)
- 9 9) 為替(JPY⇄USD)とヘッジの考え方(日本居住投資家向け)
- 10 10) 実務テンプレ(コピー用)
- 11 コアETF(米国株ETF)—まずはここから
- 12 日本上場(東証)での円建て代替
- 13 かんたん配分サンプル(“コアだけ”で完結)
- 14 補足メモ(運用のクセづけ)
1) コア銘柄の定義(前提)
- 時間軸:5~10年以上の長期保有を想定(頻繁に入れ替えない)
- 役割:ポートフォリオのリターンの“土台”を作る(安定成長+下落耐性)
- 条件:ビジネスの耐久性・構造的優位・財務健全性・株主還元・過度な割高でない
2) コア銘柄の選定フロー(7ステップ)
Step 1|投資対象の絞り込み
- 対象:時価総額上位・セクターチャンピオン・寡占/インフラ的企業・ミッションクリティカルSaaS・生活必需/医療の優良銘柄
- 除外:コモディティ価格直結で業績が大きくブレる企業、赤字継続、超高杠杆、希薄化常習
Step 2|ビジネスの“掘り”—経済的堀(Moat)
- スイッチングコスト/ネットワーク効果/ブランド/規模の経済のいずれかが強い
- 売上の50%超がリカーリング(サブスク/保守/消耗品等)だと◎
- 顧客分散(上位顧客依存<20%)/地理分散/規制耐性
Step 3|財務クオリティ(目安)
- ROIC > WACC+5%pt(少なくともROIC>10–12%)
- FCFマージン > 10%(成熟ソフトなら20%+)
- 営業利益率 安定/粗利率の長期安定(低下トレンドは警戒)
- 純有利子負債/EBITDA < 2.0、インタレストカバレッジ > 8x
- FCF/純利益 > 100%(キャッシュ化の強さ)
- 希薄化(新株発行・SBC)= 売上成長に見合う範囲
Step 4|リスク耐性(定量+定性)
- ダウンサイド・キャプチャ < 80%(S&P500比)/β < 1.1 目安
- 景気後退での需要の粘着性(必需×、ミッションクリティカル◎)
- 主要規制/訴訟/地政学リスクの把握と回避
Step 5|ガバナンス&資本配分
- 自社株買いは循環的ではなく継続性あり、配当は無理のない範囲
- M&Aの質(希薄化伴う大型M&A乱発は減点)
- 開示の一貫性、長期インセンティブの設計が株主と整合
Step 6|バリュエーション帯(“高すぎない”を確認)
- 成長株:EV/FCF < 35 or PEG < 2 を一応の上限目安
- 安定高収益:P/Eは長期平均±1σの範囲を基本線
- Zスコアや履歴レンジで“極端な割高”を避ける
Step 7|通過後の候補→最終スクリーニング
- セクター被りを調整(同じリスク要因の重複を回避)
- 米国/非米国の地域分散、USD/JPYの通貨分散も意識
3) スコアカード(テンプレ)
各項目を0~5点で採点し、重み付き平均4.0以上で“コア”合格を推奨。
| Pillar | 指標例 | 重み |
|---|---|---|
| ビジネス堀 | リカーリング比率、顧客/地理分散、Moatの強度 | 0.30 |
| 財務品質 | ROIC–WACC差、FCF/NI、レバレッジ、利益率安定 | 0.30 |
| リスク耐性 | 逆風時の需要、β/ダウンサイドキャプチャ、規制耐性 | 0.20 |
| ガバナンス | 還元方針、希薄化、M&Aの質、開示 | 0.10 |
| バリュエーション | EV/FCF、PEG、履歴レンジ | 0.10 |
- 判定:
- 4.0以上→コア採用
- 3.0–3.9→サテライト(観察/サイズ小)
- 3.0未満→見送り
4) コアのポートフォリオ設計(構成とサイズ)
- コア:60~80%
- 広範ETF(S&P500/Nas100/全世界など)+個別コア銘柄5~10社
- 1社=3~5%(最大8–10%)を上限目安。セクター上限~25–30%。
- サテライト:20~40%
- AIデータセンター/防衛/SMR/資源などテーマ、循環株、イベント駆動など
- 1案:攻め20%、守り10%(金/TIPS/ディフェンシブ)
既にS&P500・NASDAQ100をお持ちなので、ETFで土台+個別は“真に外せないチャンピオンだけ”に厳選、が合理的です。
5) 売買・リバランスの運用ルール(実務)
エントリー
- DCA(毎月一定額)をベースに、以下で追加投資:
- バリュエーションが履歴レンジ下限~中立に回帰
- テクニカル補助(長期投資の範囲内で):200日線近辺での出来高伴う反発/RSI30–40付近
追加・利確・損切り
- 追加:決算で売上/FCF/受注/RPOが健全に加速、Moat強化の材料(長期契約/規制承認/大型シェア奪取)
- 利確(部分):想定より早く**+50~100%**に到達&保有比率が目標超過/バリュエーションが履歴上限を大幅に超過
- 損切り(コアでも例外規定):
- 会計/不正/規制重大イベント
- 2期以上の連続減収+構造的理由(競争優位の消失)
- 投資仮説の崩壊(Moat毀損・単一顧客喪失 etc.)
リバランス
- 年1~2回の時間軸リバランス+ドリフト5~10%でのトリガー
- セクター/テーマの片寄りが上限超過で調整
6) リスク管理の“ガードレール”
- 単一銘柄上限:最大10%(できれば8%)
- テーマ上限:AI/防衛/資源など**各~25%**目安
- 通貨:USD資産が過度に偏る場合、JPYヘッジETFの併用や現金JPYでバランス
- 流動性:出来高が十分・ニュース/決算で早期に出入り可能
7) 3タイプの「コア構成」ひな形
A. 成長寄りコア(攻めつつ長期安定)
- ETF:S&P500 25–35%、Nas100 15–25%
- 個別コア(計20–30%):プラットフォーム/ミッションクリティカルSaaS/半導体設計・製造・EDA・装置の“トップ層”から2–4社、消費ディフェンシブで1社
- 守り:金/TIPS/ディフェンシブ 5–10%
B. 低ボラ・配当安定コア(守り重視)
- ETF:S&P500 30–40%、高配当/低ボラETF 10–20%
- 個別コア(計15–25%):生活必需/医療/規制インフラ型 3–5社
- 守り:金/TIPS 10–15%
C. ハイブリッド(バランス)
- ETF:S&P500 30%、Nas100 10–15%
- 個別コア(計20–25%):メガテック2社+ヘルスケア/必需1–2社+インフラ/金融1社
- テーマ(サテライト):AIデータセンター/防衛 10–15%
- 守り:金/TIPS 5–10%
8) モニタリング項目(決算で見るべき“定点”)
- 売上・営業/FCFの成長持続、粗利/営業利益率のトレンド
- ROICの維持/改善、在庫回転/DSOなど運転資本の健全性
- 受注/残存パフォーマンス義務(RPO)/バックログ
- 顧客・プロダクト依存の度合い、解約率/継続率
- 還元方針(自社株買い/配当)の一貫性、希薄化
- 規制/訴訟/サイバー等の新規リスク
9) 為替(JPY⇄USD)とヘッジの考え方(日本居住投資家向け)
- 原則:長期では為替は平均回帰の傾向。コアは完全ヘッジ不要が多い
- 目安:
- 極端な円安局面:新規の一部を為替ヘッジETFで(例:コアのうち1/3をヘッジ)
- 極端な円高局面:USD無ヘッジ比率を増やす(長期の為替リバウンド狙い)
- 現金は生活費12ヶ月分をJPYで確保+投資待機はUSD/JPYをバランス
10) 実務テンプレ(コピー用)
コア選定チェック(抜粋)
- ☐ リカーリング売上比率 ≥50%
- ☐ ROIC ≥12%(WACC+5%pt目安)
- ☐ FCFマージン ≥10%(SaaSは20%+)
- ☐ NetDebt/EBITDA <2.0、利払い余裕倍率 >8
- ☐ FCF/純利益 >100%
- ☐ ダウンサイドキャプチャ <80%、β<1.1
- ☐ 希薄化(SBC+増資)に節度
- ☐ バリュエーション:EV/FCF <35 or PEG<2
- ☐ 規制・訴訟・単一顧客依存の低さ
- ☐ 経営の資本配分履歴が良好
売買ルール(抜粋)
- ☐ ベースはDCA、下限帯に来たら1~2枠追加
- ☐ 目標超過&割高域→5~20%利確
- ☐ 重大リスク顕在化/仮説崩壊→即縮小/撤退
- ☐ 半年/年1で**ドリフト5~10%**調整
コアETF(米国株ETF)—まずはここから
① 超王道(米国広範 or S&P500)
- VTI(Vanguard Total Stock Market):米国株ほぼ全部(大型〜小型)に一発分散。経費0.03%。コアの最有力候補。
- VOO(Vanguard S&P 500):米国大型の中核500社に低コストで。経費0.03%。世界最大のETFに成長した実績も安心材料。
※VTIとVOOは重複大。どちらか1本でOK。
② 全世界を1本で
- VT(Vanguard Total World):米国+海外を1本で保有。経費0.06%。「シンプル最優先」派に最適。
③ 米国外(US以外)を厚めにしたい時
- VXUS(Vanguard Total International):非米国株に幅広く。経費0.05%。VTを分解するならVTI+VXUS。
④ 成長エンジン(衛星寄りだが“準コア”候補)
- QQQM(Invesco NASDAQ-100):QQQの長期向け低コスト版(0.15% vs QQQ 0.20%)。ハイテク偏重ゆえ比率は控えめに。
⑤ 質と配当成長のブレンド
- VIG(Vanguard Dividend Appreciation):増配実績のある良質企業へ。経費0.05%。守りのコアを作りたい時に。
- DGRO(iShares Core Dividend Growth):配当“成長”重視の低コスト(0.08%)。VIGと同系統。
⑥ 変動の波を和らげる“低ボラ”
- USMV(iShares Min Vol USA):下落耐性のためのクッション。経費0.15%。
- SPLV(Invesco S&P 500 Low Volatility):同趣旨。経費0.25%。景気不安時のドローダウン軽減に。
⑦ 債券のアンカー(株式100%でない場合)
- BND(Vanguard Total Bond Market) or AGG(iShares Core US Aggregate):米投資適格債の王道。どちらも経費0.03%。
- 物価連動の盾:SCHP(Schwab U.S. TIPS 0.03%) or TIP(iShares TIPS 0.18%)。
⑧ 金(コアの最後尾に少量)
- GLDM(SPDR Gold MiniShares 0.10%) or IAUM(iShares Gold Trust Micro 0.09%):株・債と相関が低い実物連動型。5%程度で分散効果。
日本上場(東証)での円建て代替
米ドル建てが買いにくい時や新NISAの成長投資枠で使いやすい国内ETF。為替“ヘッジあり/なし”の使い分けも可。
- S&P500(ヘッジなし)
- 2558:MAXIS 米国株式(S&P500) もしくはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
- 1547:Listed Index Fund S&P500(野村AM)
- S&P500(ヘッジあり)
- 2630:MAXIS S&P500(H有)(三菱UFJAM)。
- 2634:NEXT FUNDS S&P500(H有)(野村AM
- NASDAQ100
- 2568:NASDAQ100(ヘッジなし)(日興AM)
- 2631:MAXIS NASDAQ100(ヘッジあり)。
- 全世界
- 2559:MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) もしくはeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)。
ヘッジ有/無の目安:
・超長期(10年以上)で米国株の成長を取りに行く=ヘッジなしが基本。
・円高ショックの評価額ブレを抑えたい/近い将来の取り崩しあり=一部ヘッジ。
(東証にはS&P500・NASDAQ100のヘッジ版が複数あります。)
かんたん配分サンプル(“コアだけ”で完結)
- オールインワン派:
- VT 100%(極小手間)。非米国も自動で含む。
- 米国中心+海外少々:
- VTI 70%/VXUS 30%(世界時価総額比に近い)。
- 王道S&P500軸:
- VOO 80%/USMV 10%/BND 10%(成長+低ボラ+債券のバランス)。
- QQQMを“少量スパイス”:
- VTI 80%/QQQM 10%/GLDM 5%/SCHP 5%(集中リスクを他で中和)。
どの案でも年1回のリバランスと分配金の再投資をルール化するだけでOK。重複に注意(例:VTI+VOOはNG)。
補足メモ(運用のクセづけ)
- コスト最優先:長期では0.05%の差でも効きます(QQQよりQQQMを優先)。
- 分散の層:株式コア(VTI/VOO/VT)→補助(VIG/DGRO/USMV)→守り(BND/AGG・TIPS・金)の三層を意識。
- NISAで使うなら:東証版は円決済&ヘッジ選択で扱いやすい(2558/2630/2631/2559など)。